中間試験の対策受付中!!
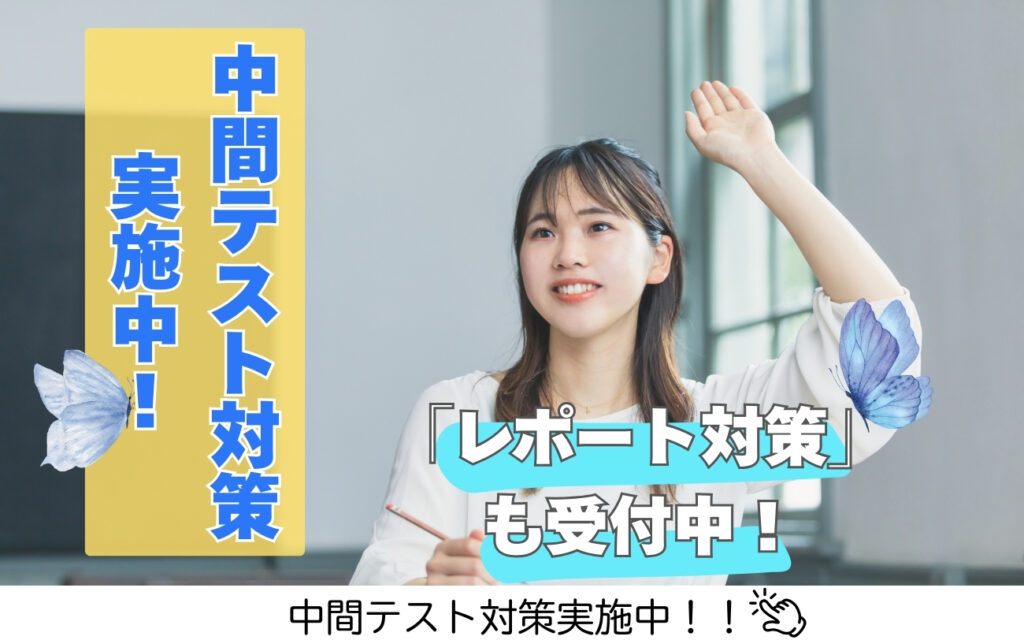
もうそろそろ中間試験
5月末~6月中旬にかけて「中間試験」を行う大学が多くなっています。
中間試験がある大学生にとっては少しずつ緊張感が高まったり、憂鬱になったりする季節だと思います。
なかには「中間試験は自信がないから、期末試験で頑張ればいいかな・・・」
と中間試験に対して諦めモードに入っている大学生もいるかもしれません。
しかし、「中間試験は大事」なんです。
・なぜ中間試験の対策が大切なのか。
・「期末だけ頑張ればいい」では本当にいけないのか
今回はこれらを確認していきましょう。
これから中間試験を迎える大学生の皆さんが
「大変だし、まだ自信もないけど頑張ってみよう」と思ってもらえたら嬉しいです。
無料相談も行っていますので、「自分だけではどうしても合格できない」大学生、
保護者の方はこちらをご利用ください。
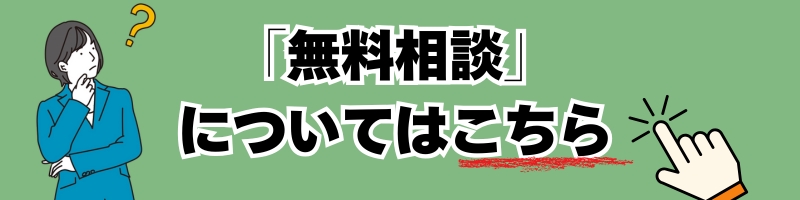
中間試験対策をする意味
前述したように「中間試験対策」はできるだけした方が良いです。
なぜ中間試験対策をした方がいいのか、その理由を紹介します。
前述したように「中間試験対策」はできるだけした方が良いです。
なぜ中間試験対策をした方がいいのか、その理由を紹介します。
「期末試験だけでの単位取得」
は難しいケースが多い
「期末試験が評価のメインだから、今回の中間試験は捨ててしまおう・・・」
「中間まではもう時間がないから、期末で頑張ろう!」
このように考える人も多いかと思います。
実際に私も学生時代はこのような悪魔の囁きがありました。
しかし、実際には中間試験で点数が全く取れないと期末試験での挽回は難しいケースが多いです。
これは大学の単位の評価方法が大きく関わります。

中間試験の評価は全体の2~5割程を占める
大学の単位の評価方法は科目ごと、担当の先生ごとに変わります。
シラバスを見てもらうと
「中間試験30%、期末試験50%、提出課題20%」
「中間試験50%、期末試験50%」
「中間試験20%、期末試験80%」
などと記載されていると思います。
科目や担当の先生によって比率は変わりますが、おおよそ「20%~50%」になっていることが多いです。
中間試験で点数が取れなかった場合、期末試験で何割を取ればいいのかを見ていきましょう。
「中間試験の評価割合が20%」の場合
前述のように中間試験の比率は20%~50%になっていることが多いです。
まずは中間試験の点数の影響が少ない
「中間試験20%(中間試験20%、期末試験80%)」を例に考えてみましょう。
もしも中間試験の点数が0点だとすると、合格までの60点を全て期末試験で取らなければいけません。
ここで大切なのは「100点中の60点を取ればいいわけでは無い」ということです。
今回の例は「中間試験20%、期末試験80%」です。
つまり、期末試験の配点はもともと80点しかありません。
この80点のうち、60点を取らなければいけません。
80点中の60点なので、期末試験では「75%」を取らなければいけないことになります。
もともとの合格ライン60点が75点まで上昇するので、急にハードルが上がることが分かると思います。
※これはあくまで「中間試験の点数の影響が少ない(全体の20%)」の場合です。
もしも中間試験の点数が0点だとすると、合格までの60点を全て期末試験で取らなければいけません。
ここで大切なのは
「100点中の60点を取ればいいわけでは無い」
ということです。
今回の例は
「中間試験20%、期末試験80%」です。
つまり、期末試験の配点はもともと80点
しかありません。
この80点のうち、60点を取らなければいけません。
80点中の60点なので、期末試験では「75%」を取らなければいけない
ことになります。
もともとの合格ライン60点が75点まで上昇するので、急にハードルが上がることが分かると思います。
※これはあくまで「中間試験の点数の影響が少ない(全体の20%)」の場合です。
「中間試験の評価割合が30%」の場合
「中間試験の評価割合が30%」の科目を期末試験だけで合格しようとするとどうなるでしょうか。
課題点がないと仮定すると、
「期末試験の評価割合は70%」になります。
合格ラインは60%なので「期末試験の70点のうち、60点を取らなければいけない」ことになります。
これは期末試験で85%を正解しなくてはならない計算になります。
実際の成績で85%はかなり好成績の部類にはいるため、苦手科目の場合は相当頑張らなくてはいけません。
「中間試験の評価割合が50%」の場合
「中間試験の評価割合が50%」の場合、期末試験の評価割合は残りの50%になります。
合格ラインは60%なので、期末試験で満点を取ったとしても足りないことがわかります。
つまり、中間と期末がそれぞれ50%の科目では中間テストが0点だと期末試験での挽回はできないことが分かります。
ちなみに「中間試験が100点中20点、期末試験が満点(100点中100点)」の場合が合計60点でギリギリ合格ラインになります。
0点は極端な例かもしれませんが、今回のようなケースでは
「最低でも中間試験で20点はないと、期末試験が満点でも単位はもらえない」ことになります。
「期末試験で満点」が取れるのはごく少数なので、実際には中間試験で100点中の40点はほしいところです。
「中間試験の評価割合が50%」の場合、
期末試験の評価割合は残りの50%になります。
合格ラインは60%なので、期末試験で満点を取ったとしても足りないことがわかります。
つまり、中間と期末がそれぞれ50%の科目では中間テストが0点だと期末試験での挽回はできないことが分かります。
ちなみに「中間試験が100点中20点、期末試験が満点(100点中100点)」の場合が合計60点でギリギリ合格ラインになります。
0点は極端な例かもしれませんが、今回のようなケースでは
「最低でも中間試験で20点はないと、期末試験が満点でも単位はもらえない」
ことになります。
「期末試験で満点」が取れるのはごく少数なので、実際には中間試験で100点中の40点はほしいところです。
「期末試験よりも点数がとりやすい」
ケースが多い
ここまでは「中間試験対策の大切さ」を単位評価の割合の面から紹介しました。
もう1つの理由が「試験の難易度」です。
難易度の面で期末試験よりも中間試験の方が対策しやすい科目が多くなっています。
学期の前半の内容の方が理解しやすい
大学の授業は学期ごとに第1回~第15回で組まれていることが多いです。
第1回でガイダンスや導入的な内容を扱い、最後の15回目にかけてその単元の深い内容に入っていくことが多いです。
そのため、「1回目~7回目までの内容」と「8~15回目までの内容」を比べた時に、
「後半の8~15回目の内容の方が難しくなっていることが多い」です。
特に数学はこの傾向が強いです。
このことから、中間試験の範囲の方が期末試験よりもまだ理解しやすい内容になっているケースが多いです。
期末試験の範囲を「学期の全て」とする先生もいる
多くの授業では中間試験のテスト範囲は1~7回、8回目が中間試験で
期末試験の範囲は中間試験以降の内容(9~15回)となっていることが多いです。
しかし、「期末試験の範囲はその学期の内容全て」とする先生もいます。
こうなると試験範囲は単純計算で中間試験の2倍になります。
このケースでは中間試験の対策が中間試験の対策でもあり、期末試験の対策にもなります。
また、そもそも中間までの前半の範囲が分からないと後半の範囲も理解できない科目もあります。
可能な限り中間試験の対策は行いましょう!
高得点を取れなくても、対策はしよう!
このように仮に中間試験で高得点が取れなかったとしても、
少しでも点数を稼ぐことで期末試験のハードルは変わります。
現時点で「理解できない内容が多い」「試験まで時間がない」と思っていても、あきらめずに少しでも点数が取れるように対策をしましょう。
クォーター制の大学では期末試験
クォーター制の大学では1年を4分割してそれぞれの学期で成績が出ます。
前後期制の試験が「春学期の中間試験(5月下旬~6月)、春学期の期末試験(7月下旬~8月上旬)」と分かれているのに対して、クォーター制では「春学期の期末試験(5月下旬~6月)」と「夏学期の期末試験(7月下旬~8月上旬)」となります。
つまり、中間試験の時期に期末試験があり、その試験で春学期の成績が決まります。
前後期制の大学以上に、この時期の試験が大切になります。
評価制度を確認して、優先順位をつけよう
もちろん、履修している科目全部の中間試験対策ができるのが理想です。
しかし、科目が多く時間が限られる状況では全ての科目を十分に対策するのは難しいかもしれません。
そんなときは優先順位をつけて対策をしましょう。
「必修の科目」で「中間試験の評価割合が高い科目」ほど優先順位は高くなります。
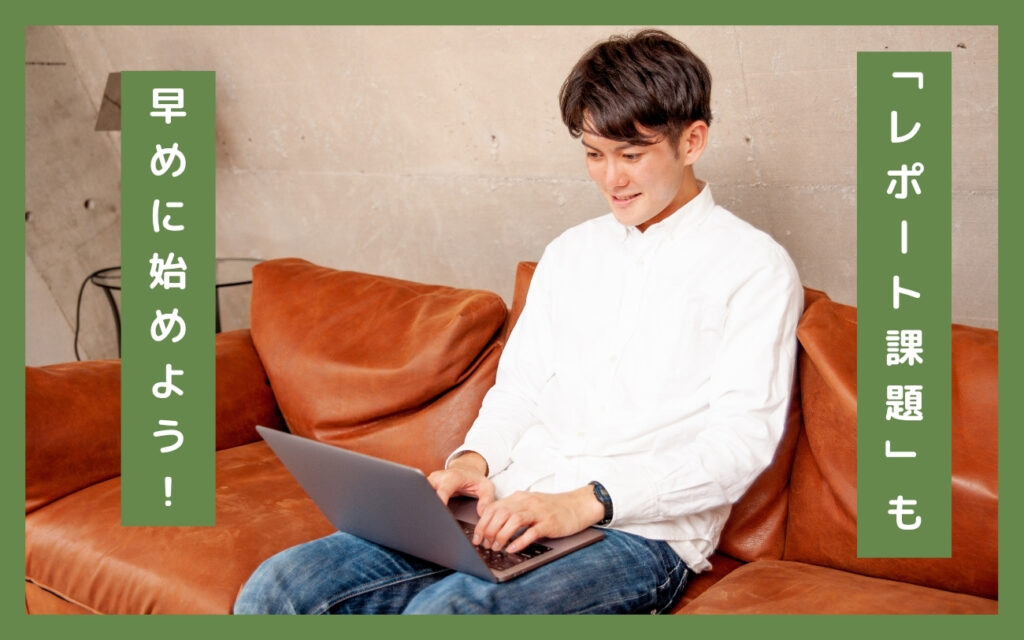
課題・レポートの対策も可能!
ここまで中間・期末試験といった「テスト」に焦点を当てて話してきました。
科目によっては「課題(レポート)」で単位が決まるものもあります。
試験と違い、レポートは制限時間がなく、教科書や授業スライドを参照しながら作成できます。
そのため「レポートなら試験よりも簡単にできるのでは?」と思うかもしれません。
しかし、実際には内容を理解していないと解けないケースも多いです。
教科書と全く同じ問題は出ない
教科書や授業スライドと同じ問題をレポートに出す先生は少ないです。
理解できていないと自分では解けないケースも少なくありません。
ネットやYouTube、参考書に解説がない
高校生までの勉強は参考書が多く、YouTubeなどで問題の解説をしている人も多いです。
そのため、それらを参考にして課題に取り組むこともできたと思いますが、
大学の勉強は参考書自体が少なく、YouTubeなどに解説を載せている人もほとんどいません。
そのため、理解できていない問題のヒントを見つけるのも大変な学生が多くなっています。

チャットGPTは対策され始めている
チャットGPTをはじめとする生成AIに課題をやってもらう行為も危険になり始めています。
先日、慶應義塾大学の総合政策学部で生成AIをしようすると間違った答えが出される対策を学校側が取ったニュースが話題になりました。
このようにチャットGPTをはじめとする生成AIを使用した課題の回答作成は徐々に危険になっているため、やめた方が良いです。(あくまで「分からない部分を理解をするための補助ツールの1つ」として使う分にはありだと思います)
そもそも大学側は生成AIの使用を推奨していないケースが多く、推奨する場合もルールを設けている先生が多いです。
マイゼミナールでは「課題のサポート」も可能!
マイゼミでは課題・レポートの対策も行っています。
提出日に間に合うよう、スケジュールを決めてサポートを行います。
「大学生のための塾」の「完全個別授業」だからこそ、実際に出ている課題を先生と取り組めることが強みです。
期末試験でも困らないよう、答えを教えるだけでなく「なぜそうなるのか」を理解できるように授業を行います。
※課題の代理執筆ではありません。
あくまで先生と一緒に、分からないところを教わりながら進める授業です。
困ったら無料相談をご利用ください

「中間試験や課題(レポート)で困っている」
「すでに大学の授業についていけてない」
「誰かに相談したい、教えてほしい」
こんな状況の大学生、保護者の方は無料相談がおすすめです。
大学生からの相談対応が豊富な相談員がご対応いたします。
「自分の状況ではテストまで費用はいくらかかるの?」などにもお答えできます。
お困りの方は下記よりお申込みください。
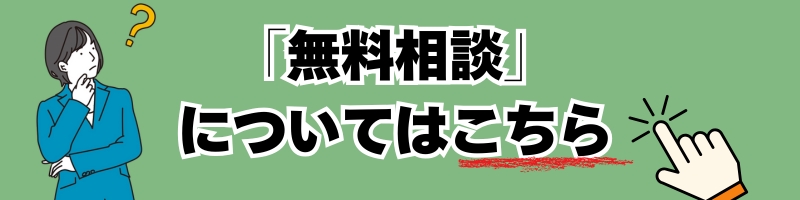
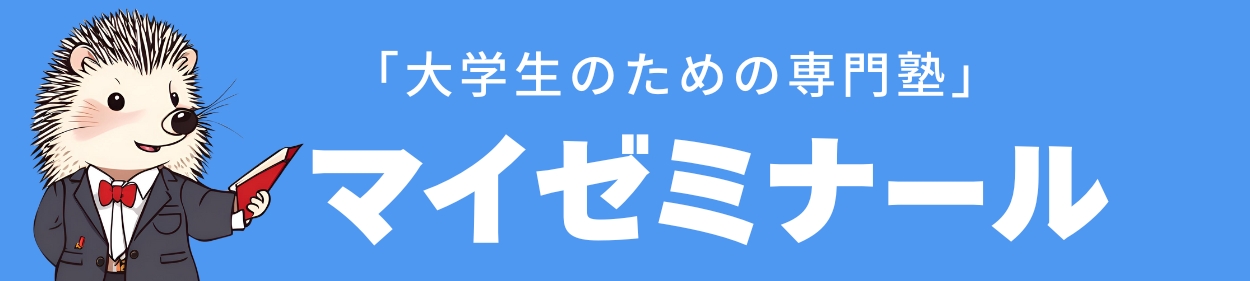





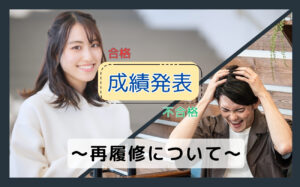




コメント